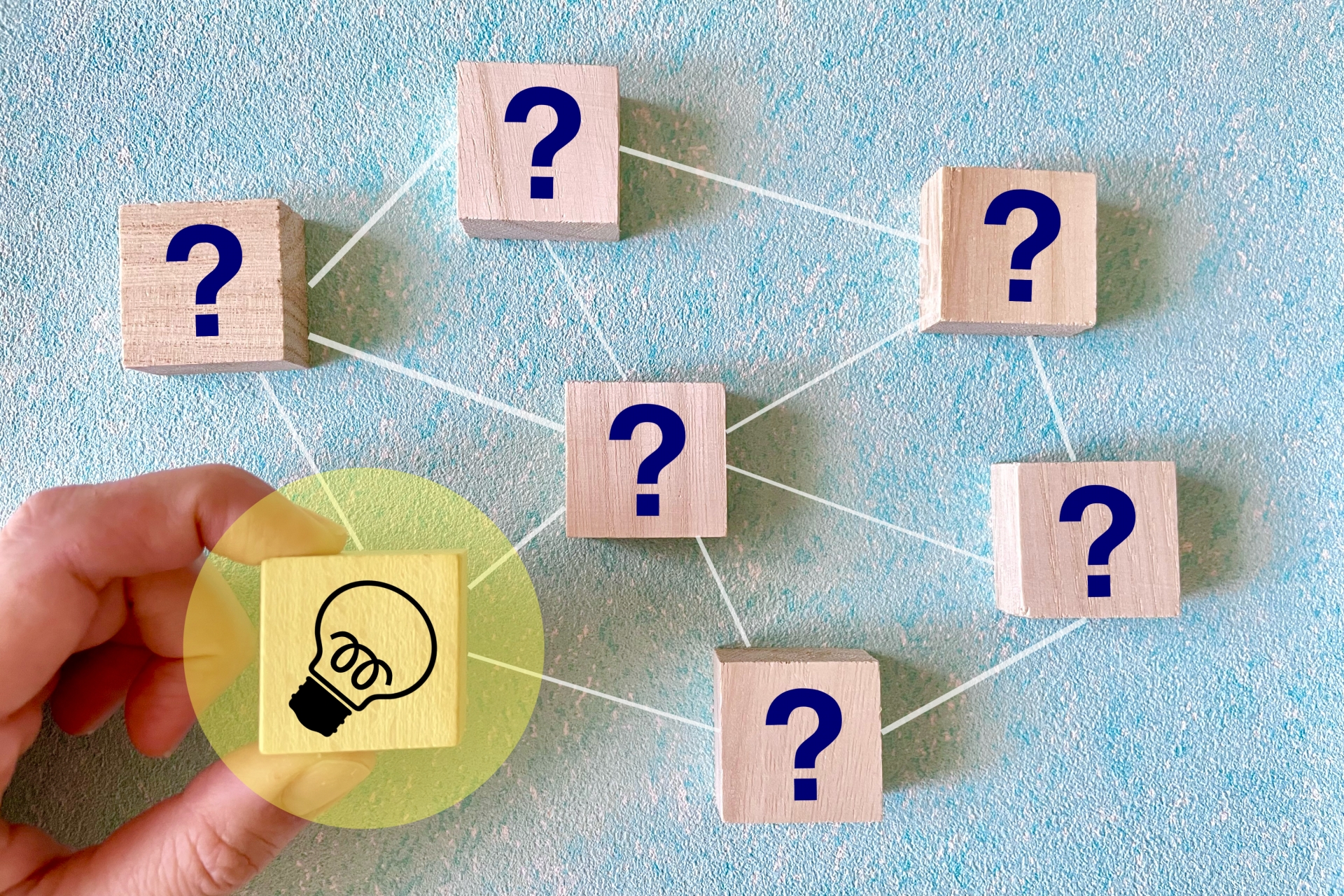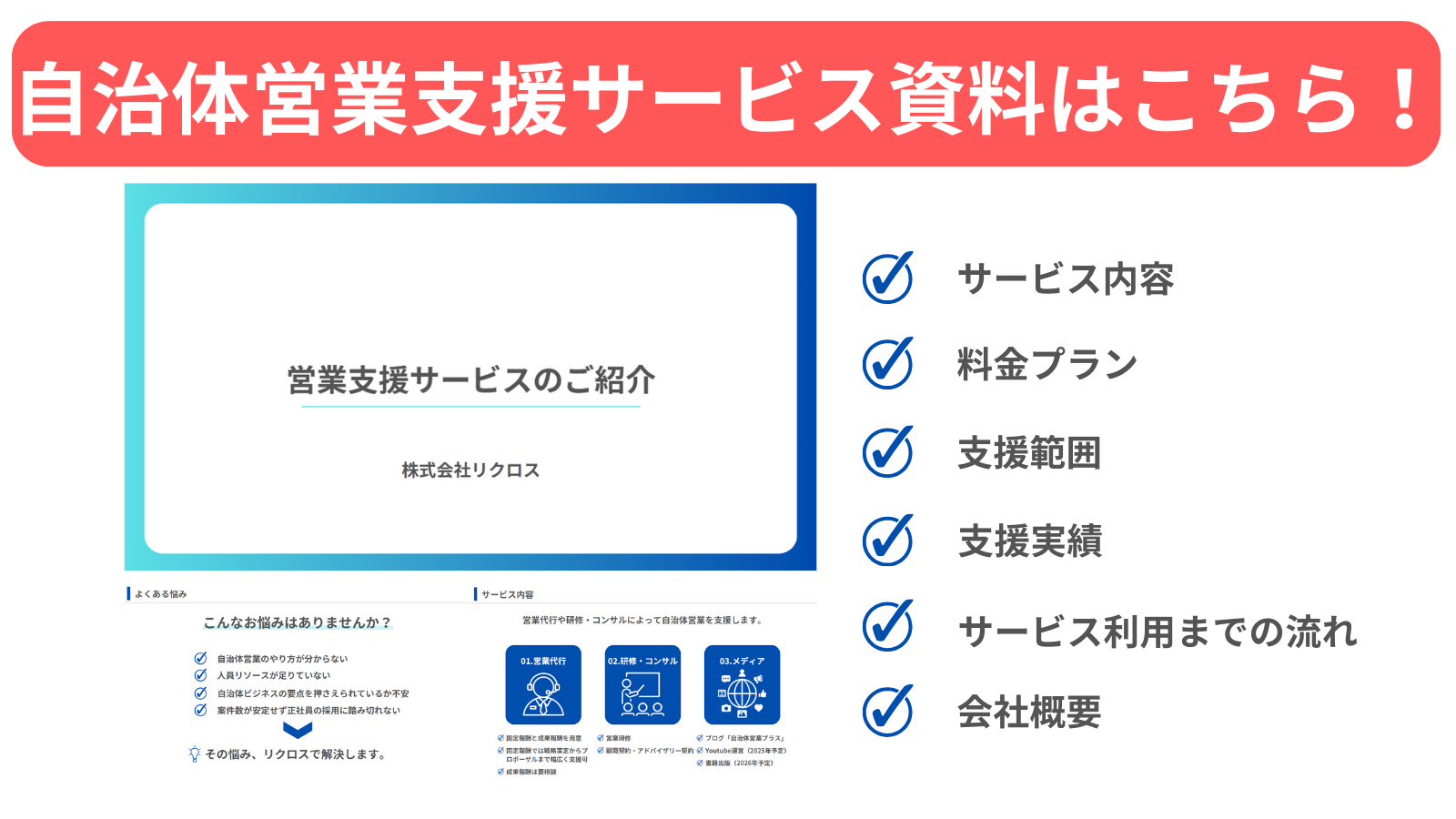はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体営業において「刺さる」ポイントと「刺さらない」ポイントについて解説していきます。
自治体営業や法人営業、個人営業は同じ「営業」という意味で共通点が多くありますが、刺さるor刺さらないポイントという観点では、世間的なイメージより違いが多くあります。
記事をお読みいただき、自社サービスの訴求ポイントを考えるきっかけとなれば幸いです。
自治体営業において「刺さる」ポイント
実績が(豊富に)ある
自治体ビジネスの魅力の一つとして、実績を自治体間で横展開しやすいことを上げました。
行政が世間から厳しい目を向けられていることと、各自治体で課題が似通っていることから、「他自治体が導入しているならうちの自治体でも導入してみよう」となりやすい傾向があるのは間違いありません。
法人向けサービスや個人向けサービスにおいても、実績があると営業活動が有利に働くのは間違いありませんが、自治体の方がより顕著なように思います。
「トヨタがいちばん売れているからトヨタにしよう」「このチョコがいちばん売れているからこれにしよう」という理由で購入を決定する個人の方は少ないでしょうが、「このサービスがいちばん導入実績が多くて安心できるから、これにしよう」という自治体の割合はけっこう多いです。
自治体営業の際は営業資料で導入実績をしっかり訴求しましょう。自治体営業の資料作成のポイントに関する記事も是非ご覧ください。
自治体ビジネス未参入の企業様はまず少数の自治体とじっくり関係を構築し、手堅く導入実績をつくることをオススメします。
問い合わせやトラブル時のフォロー体制
自治体職員は新しいサービスを導入する際、運用後のフォロー体制を重視します。
実際にプロポーザルの評価基準で「業務の実施体制」などの形で項目が設置されていることも多いです。評価基準や採点表は職員の方がプロポーザルの準備をする上でテンプレート(様式)として庁内に共有されていることが多く、評価の一項目として含まれることが非常に多いでしょう。
トラブルが発生した際に迅速に対応でき、問い合わせへ早くレスポンスできる体制を構築し、しっかりと訴求できるようにしておきましょう。
例えば、「365日対応のコールセンターがあり、自治体専用のサポート窓口を設けています」「導入後期間中は無料で定期フォローを行います」といったフォロー体制を明示すると、安心感を与えられます。また、自治体内での運用を支援する研修会の実施や、職員向けのマニュアル提供も評価されやすいポイントです。
国や都道府県の方針・制度に沿っている、補助金や助成金がある
自治体の事業は、国や都道府県の方針に沿って進められることが多いので、営業提案もこれらの方針と合致していることが重要です。「自治体DX」「カーボンニュートラル」「デジタル田園都市構想」など、現在の政策テーマに紐づけることで、職員にとって説得力のある提案になりますね。
また、補助金や助成金が活用できる提案は、予算確保のハードルを下げるので有効です。例えば「このシステムは、○○省の○○補助金の対象になります」と伝えることで、職員側も導入の検討がしやすくなります。
具体的に、どの補助金が活用できるのか、補助率はどのくらいか、申請方法はどうすればよいのかまでサポートすると、さらに刺さりやすくなるでしょう。
なお、商談に参加する自治体職員の方が必ず国や都道府県の動向を把握しているとは限らないので、資料に落とし込んだり口頭で触れたりする形で会話しましょう。
自治体営業において「刺さる」ポイントとして以下の3点を挙げました。
- 実績が(豊富に)ある
- 問い合わせやトラブル時のフォロー体制
- 国や都道府県の方針・制度に沿っている、補助金や助成金がある
これらは抽象化してまとめると「低リスク」「説明しやすさ」となりますので、公共領域への営業の際は常に「低リスクを訴求できているか?」「相手が説明責任を果たしやすいか?」という点をチェックしましょう。
自治体営業において「刺さらない」ポイント
前段で挙げた「低リスク」「説明しやすさ」という2点に触れつつ、自治体営業において「刺さらない」ポイントを挙げていきます。
価格の安さ
法人営業では「コスト削減」が大きな魅力になりますが、自治体営業では単に価格が安いだけでは響きません。むしろ、「なぜこんなに安いのか?」と品質やサポート体制に不安を感じられることもあります。
実際に多くの企業様の自治体営業を支援していますが、自治体職員の方との商談において「想定している予算を超えないかどうか」は確認されることが多いですが、「予算内でいかに最小限のコストになるか」はあまり詰められません。
自治体は「適正価格で長期間安定的に運用できるかどうか」を重視します。そのため、「安価であること」よりも「この価格でしっかりと運用・保守ができる仕組みがある」という点をアピールしたほうが効果的です。
価格の安さは「低リスク」であることの「説明しやすさ」には繋がりません。
最新技術の活用
AI、ブロックチェーン、IoTなどの最新技術は注目されますが、それを前面に押し出しても自治体には響きにくい傾向があります。
新しくなじみのないものは不安に繋がるので、「低リスク」であることの「説明しやすさ」とはかけ離れていることが分かるでしょう。
自治体にとっての顧客である住民も、ほとんどが最先端の生活よりかは安心安全の生活を求めているはずです。
初期費用を抑えてランニングコストに分散
民間企業向けでは「初期費用を抑え、月額課金モデルにする」ことが歓迎されることが多いですが、自治体では逆に敬遠されることがあります。
自治体の予算は年度ごとに決まっており、毎年のランニングコストが発生するよりも、一括購入や補助金を活用した導入のほうが進めやすい場合があります。
そのため、「一括での導入プランも用意」「年度内の補助金を活用できる」などの選択肢を示すことが重要です。
人口減少とそれに伴う税収減が進む中で、将来の継続支出が発生することは「低リスク」ではないでしょう。よって、「説明しやすさ」からは離れていることが分かります。
使いやすさ・UIの良さ
民間企業では「直感的な操作性」や「洗練されたUIUX」が強みになりますが、自治体ではそれほど評価されません。
UIの優秀さが導入の決め手になるのであれば、「行政のシステムは使いづらい」といった声はもっと減っているはずです。
「UIの良さ=使いやすさ・見やすさ」ではありますが、「UIが良いサービスよりも、使い慣れているサービスの方が使いやすい」という視点が抜けないようにしましょう。
短期導入・契約期間が短いプラン
自治体の意思決定には時間がかかり、すぐの導入は求められていません。また、サービスがダメだったから利用をやめた場合、褒められるよりマイナス評価を受けることが多いのはほとんどの職員の方が同意するはずです。
言い方を変えると、「気軽に試してダメならすぐに撤退」よりも「絶対に失敗しないこと」の方が価値が高いです。
「短期導入可能」「1年契約からOK」といった柔軟性は必ずしも強みにはならず、むしろ、長期的に安定運用できるかどうかを重視されるため、「5年以上の運用実績」「長期サポートの提供」などの点をアピールした方が効果的です。
法人や個人向けの成功事例
自治体ビジネス参入初期は法人や個人向けの成功事例があると良いですが、「加点ポイント」ではなく「多少の安心ポイント」程度の認識でいましょう。
プロポーザルの採点基準で自治体の実績を問われることが非常に多いですが、法人や個人向けの実績を問われているのを見たことはありません。
自治体ビジネスに本格的に取り組みたい企業様は、法人や個人向けの実績を重ねるよりも、早期に自治体向けの実績を積み重ねることをオススメします。
地域活性や公益性の協調
サービス導入により地域活性に繋がることや、サービス自体に公益性があることを強調される方もいると思いますが、それらは「大前提の話」「当たり前の話」なので、それだけで職員の方の心が動くことありません。
地域活性や公益性の訴求は、クーラーを買いたい個人に対して「このクーラーを使うと涼しくなりますよ」と言っているようなものです。コストが安い、タイマー機能がある、とにかく売れているなど、もう少し深い訴求をするようにしましょう。
最後に
自治体営業において「刺さる」ポイント「刺さらない」ポイントについて書いてきました。
文中でも触れましたが、「低リスク」「説明しやすさ」の2点が刺さるor刺さらないを分けるポイントです。
是非定期的に記事を見返していただき、適切な訴求ポイントを押さえてください。