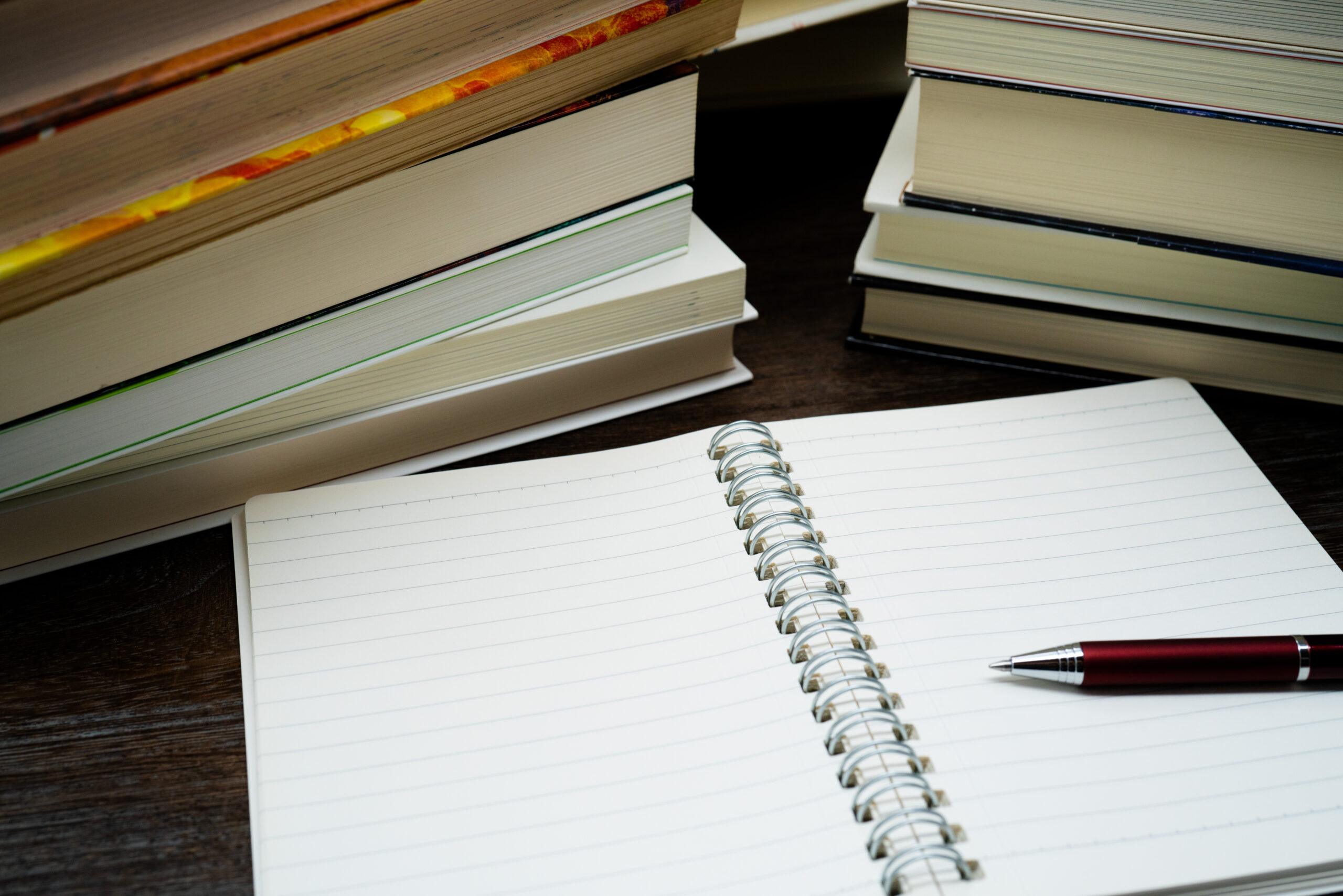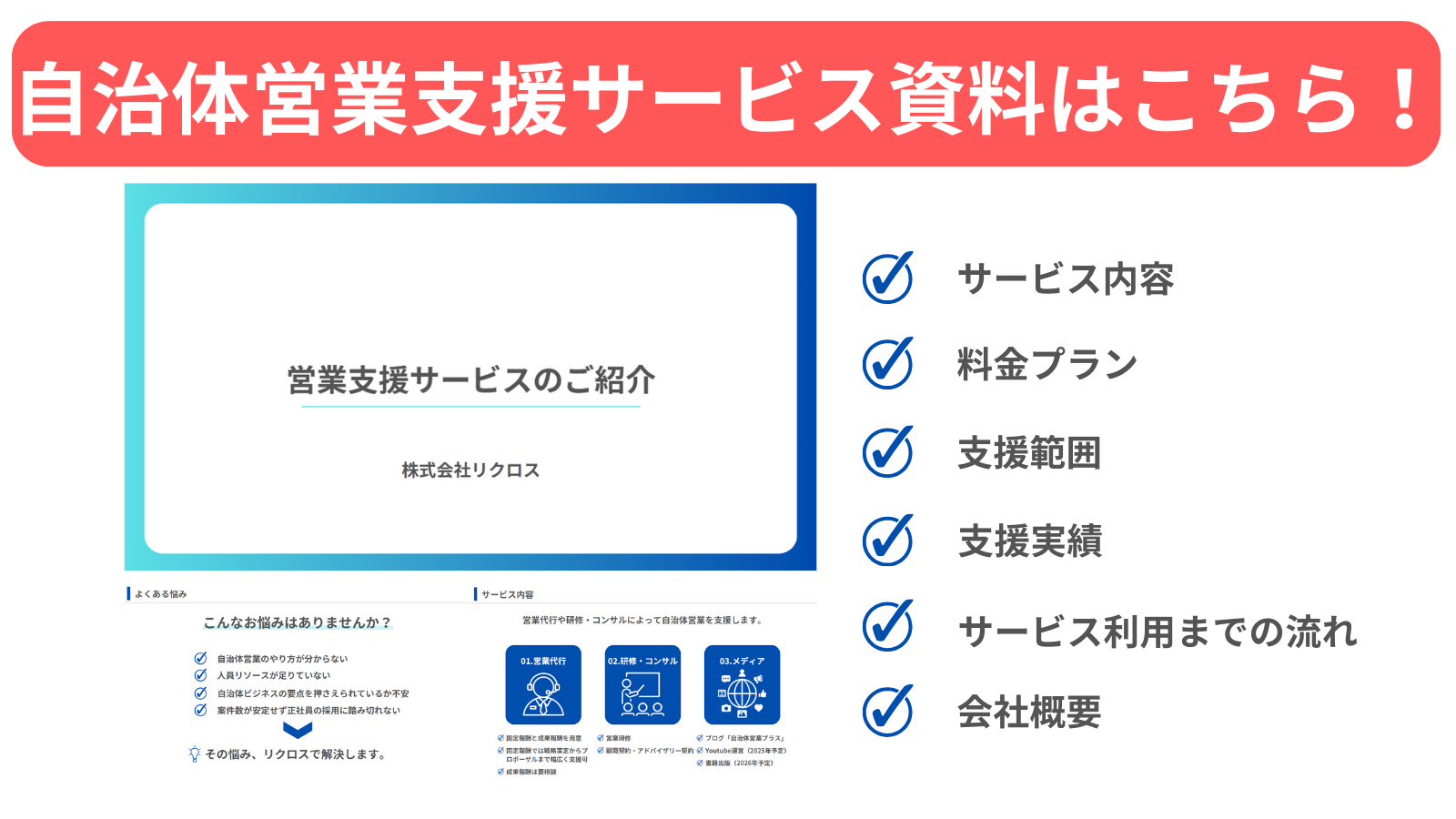はじめに
こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は読書メモvol.2として『マンガでわかる!自治体予算のリアル』を元に、自治体営業に取り組む企業様向けにメモを書きました。
どちらかというと自治体職員向けの本ではありますが、読みやすく、かつ職員の方の様子が視覚的にイメージを掴められるので、マンガの部分だけでも読むのもありかなと思います。
執筆に関わったのが財政課長経験者と現職教育長、マンガが描ける自治体職員とのことで、リアルさは間違いないでしょう。
それではよろしくお願いいたします!
メモ
“郵便物のとりまとめは総務課の仕事だ 仕事が増えるとあっちゃ、いくら安上がりでもはいよってわけにはいかんだろ”
市民課の職員がコストカットの提案をしたものの、上記発言者(総務課)の仕事が増えるので嫌がっているシーンです。
部署をまたぐ営業活動になる企業様もいらっしゃると思いますが、このような状況を乗り越えるにはどのようにアプローチしていくのか、私も含め一生のテーマになると改めて思いました。
- 熱量溢れる担当者がいる自治体に注力する
- 長期的に信頼関係を構築し、気持ちよく動いてもらう
- 距離や人口規模の近い自治体の実績を示す
- 旬な情報とセットでアプローチする
- トップアプローチする(担当者への配慮はもちろん忘れず)
等々いろいろ考えられますが、少しでも成功率を上げるために試行錯誤することがまずは大事だと思います。
“肉付け予算が骨格予算の1%以下という例も少なくありません。つまり、予算の大半の使途は決まっているのです。”
マニアックな内容なので用語は覚える必要ありませんが、「骨格予算」は法令などに基づく義務的経費や既存施設の維持管理費など、必要最小限の経費です。
“肉付け予算が骨格予算の1%以下という例も少なく”ないとなると、ほとんどが前例踏襲的な骨格予算であって、肉付け予算を活用して市場にない新たなサービスを導入してもらうのは簡単ではないことが分かります。
逆に言うとほとんどの予算は例年と同じような内容なので、すでに自治体が取り組んでいるものをリサーチし、リプレイスするような提案は有効だと改めて思いました。
業務改善の余地があるのは自治体の方々がいちばん分かっているはずですので、その改善案として企業様の魅力的なサービスを開発・提案していただければと思います。
(また、公務員の皆様のお困りごとはビジネスの種なので、どんな形であれどんどん発信していただきたいと思います。)
“枠配分方式”
財政担当課が存在することはほとんどの企業様がご存知だと思いますが、「一件査定方式」と「枠配分方式」については知らない企業様が多いのではないでしょうか。
「一件査定方式」では予算要求内容を一つずつ財政担当課が確認していきますが、「枠配分方式」は枠(予算)の範囲内であれば予算を要求課の裁量に任せるものです。
別の言い方をしますと、予算要求した内容全てに〇×がつくと思っている企業様が多いと思いますが、予算要求課(営業先の部署)が枠に入れてくれたら(ほぼ)財政担当課の査定はクリアします(また、現在では「枠配分方式」の方が主流のようです)。
多くの自治体で「財政課に切られたくない予算は必ず枠(予算)に入れろ」といった会話がされているのではないでしょうか。
枠に入るのは先ほどで言う「法令などに基づく義務的経費や既存施設の維持管理費」がメインなので、企業様の営業で変更できないことの方が多いですが、スクラップ&ビルドにより新規事業が枠内に入ることも。
財政担当課のロジカル査定を受けず、要求課の熱意や創意工夫により枠内に入る可能性もゼロではありませんので、しっかりと熱意をもって必要性を訴求しましょう。
“復活要求”
「復活要求」は、企業に知られてしまうと連絡が多くなって大変になるので、自治体職員から企業にはわざわざ教えない仕組みだと思います。
1月に実施されることの多い「復活要求」とは、財政担当課で0査定(≒予算をつけないという判断)だったとしても、予算要求課の希望により市長に直接査定を依頼できる仕組みです。
企業だと「社長以下はNGだけど社長がOK出しちゃった」みたいなことはいくらでもありますが、自治体でも同じことが全然あり得るのです。
何を復活要求するかは予算要求課の判断なので、要求課の温度感を高く保たせるのが非常に重要でしょう。
こういった理由からも、年1回だけでなく複数回アプローチして関係構築し、熱量をキープしておくのが大事です。
最後に
「自治体職員向けの本を、自治体ビジネスに取り組む企業様向けに」ということで書いてみましたが、いかがでしたでしょうか。
個人的には、今日取り上げた内容を知っているかどうかで自治体営業の考え方も変わると思うので、引き続き同じような記事を書けたらいいなと思いました。
読書メモはこれからもどんどん書いていきます。
今後もよろしくお願いいたします!