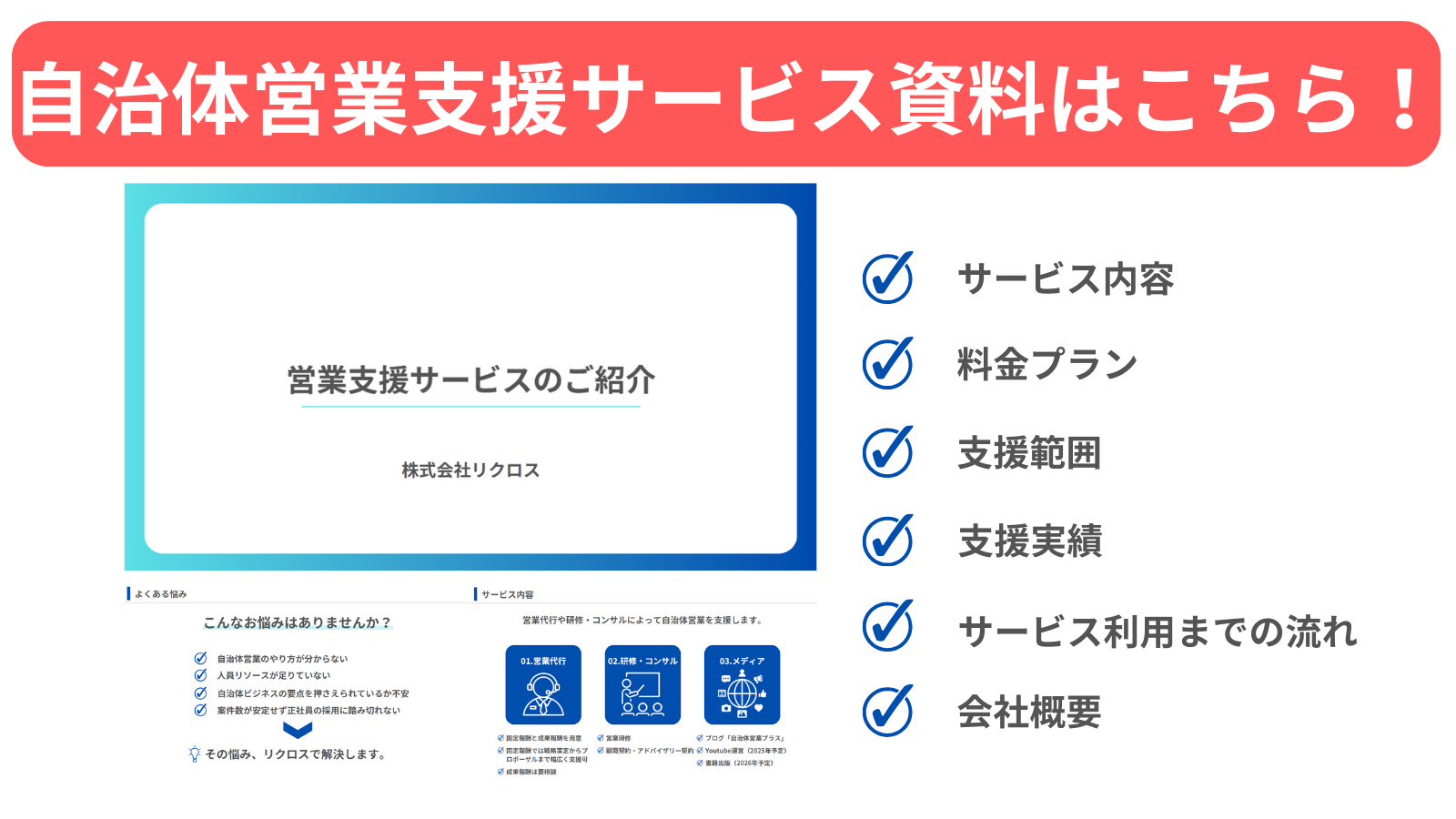はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
普段と急にテイストが変わりますが(笑)、今回は自治体ビジネスにおけるデジタルマーケティングについて考えてみたので、まとめていきます。
自治体営業のコツや自治体営業のスケジュールについては別途記事がありますので、是非ご覧ください。
自治体ビジネスとデジタルマーケティングの現状
私自身これまで営業経験しかありませんが、本メディアを始めてからマーケティングについても考えるようになりました。
どこかで「営業は1対1のマーケティング」という言葉を見たことがありますが、まさにそのとおりですね。逆に、こういったメディアだと1対Nで発信できるので新鮮な感覚で楽しんでいます。
さて、自治体営業において、2024年12月時点ではプッシュ型営業が中心となっています。架電や訪問、メールなどですね。
多くの業界ではデジタルマーケティングは当たり前になってきていますが、自治体ビジネスにおいてはどのようになるのでしょうか?
自治体は今でもインターネットに直接アクセスできる環境に限りがあり、業務で使うPCが仮想端末や専用ネットワークに限定されていることが多いです。
私が在籍していた時は、PCで情報収集したことはありますが広告を見た記憶がないですし、能動的な検索以外で打ち合わせなどに繋がったことはありません。
デジタルマーケティングが自治体ビジネスにどう影響するのか?
デジタル技術の進展や自治体のDXへの取り組みが進んでいますが、企業が自治体へ営業するプロセスに限って言うと、DXが進んでいるようには到底思えません。
自治体の普段の業務を効率化したり、住民サービスの質を高めたりするのが優先なので、自治体営業する企業向けの配慮なんて当然しないでしょう。
自治体営業においてデジタルマーケティングができるようになったとしても、それは自治体営業する企業のためではなく、他の何かしらの取り組みによる結果に過ぎない未来が見込まれます。
当分の間はせいぜいウェビナー(Webセミナー)が続くくらいで、自治体向けに一般的なWeb広告やSNSマーケティングが行われて成果が出るイメージは個人的にはありません。
改めて、架電などのアナログ(だけど自治体営業において有力)なアプローチに注力していこうと思いました。
最後に
記事を書くにあたっていろいろな角度から考えてみましたが、「自治体営業の手法が大きく変わるとは思えないな」と改めて感じました。
弊社も自治体営業を支援する上で、オーソドックスに架電やオンライン商談、訪問商談など磨いていこうと思った次第です。
今回もお読みいただきありがとうございました!