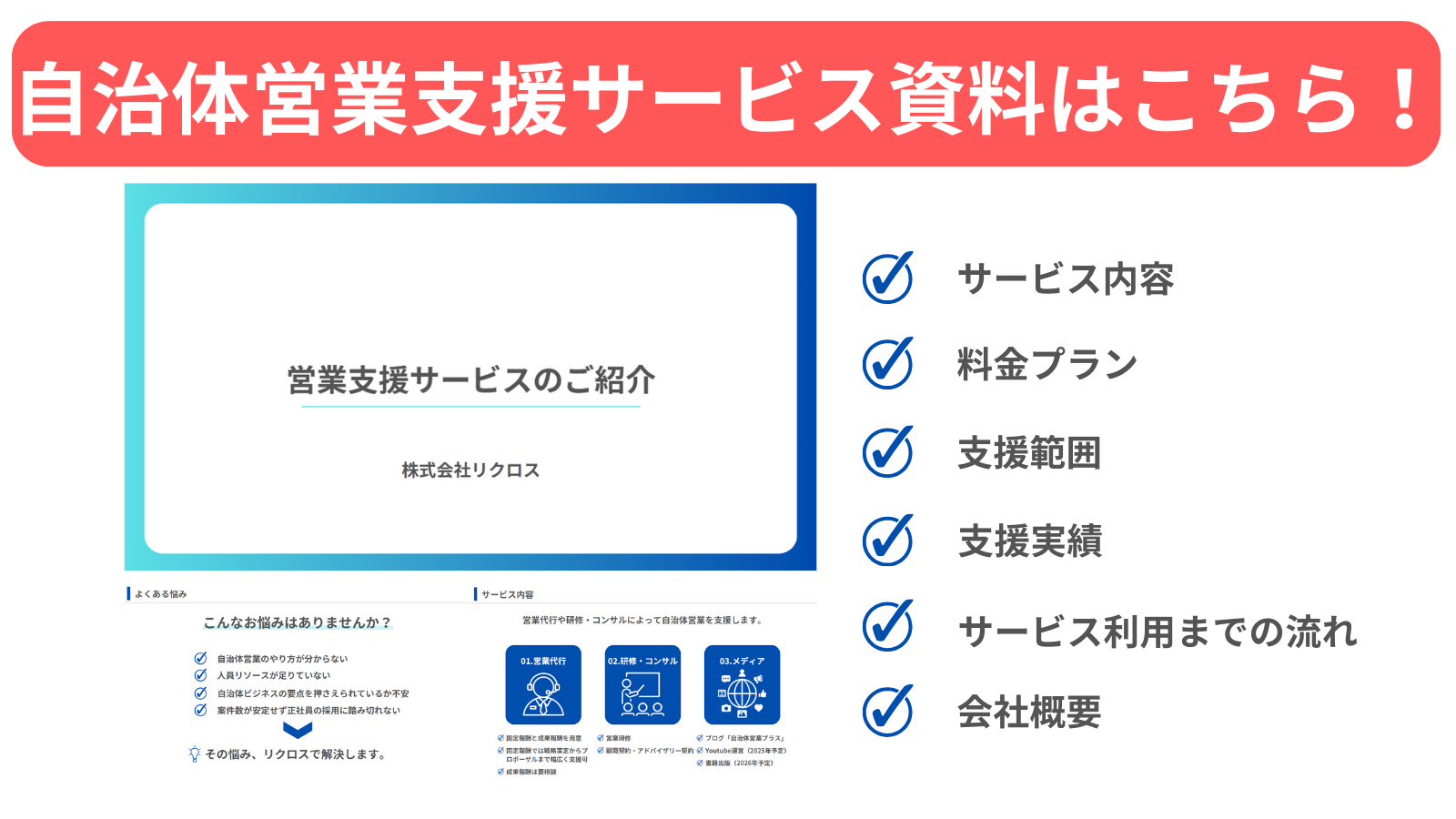はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は「自治体営業は難しいか?」について私なりの見解を書いていきます。
世間的には「難しい」「取っつきにくい」「面倒が多そう」という印象があると思いますが、本記事をご覧いただいて自治体営業を考えるきっかけとなれば幸いです。
それでは早速見ていきましょう!
自治体営業は難しい?に対する回答
まず結論から書きますと、「自治体営業=特殊で難攻不落な分野」ではなく、「他の法人営業先と同様、独自のクセやルールが存在するひとつの市場」という認識です。
あっさり言うと、自治体営業は「ちょっとクセのある法人営業」に過ぎず、「難しい…」と頭を抱えるような分野ではないと考えています。
実際、自治体営業で困難に感じられる点の多くは、「ビジネス相手が自治体であるが故に発生する固有の慣例やプロセス」から来ています。
しかし、それらは「厳密な社内稟議が必要な大企業相手」や「独自の承認プロセスや規格が存在する特殊業界」の法人営業における特殊要件と本質的には大きく異ならない、とも言えるでしょう。
自治体営業が法人営業と似ている点
自治体営業は「ちょっとクセのある法人営業」ということで、具体的に5つの観点で解説します。
意思決定が遅い
意思決定が遅いのは、民間大手にもありがちな事情でしょう。
大企業やグローバル企業でも意思決定には多くのステークホルダーが関わるため、商談成立までに時間を要します。
自治体の場合も同様に、担当部署や上司、場合によっては議会や住民の理解と合意が必要となるだけで、「多層的な承認プロセスがある法人への営業」と考えれば、全く特別なことではないでしょう。
独特のルールや制度の存在
自治体営業における独特のルールや制度の存在は、法人営業における業界特有の規格・安全基準などと類似しています。
自治体には入札制度や補助金交付基準などに基づく手続きを要することがあり、それらが「難しい」と思われがちです。
しかし、建築業界であれば建築基準法や各種認証、医療業界であれば薬機法対応といった業界特有のルールへの適応が不可欠。
自治体営業も一つの「業界規則」と認識すれば、特異なハードルではなく「慣れれば対処できるルール」でしかないでしょう。
関係構築に時間がかかる
自治体営業で関係構築に時間がかかるのは、法人営業における既存顧客の深耕営業と同じです。
自治体職員は異動が多く、人間関係をゼロから築く必要が出てきますが、多くの法人営業でも担当者が変わったり、組織再編により取引条件を再交渉したりするケースは全く珍しくありません。
既存顧客との関係維持という観点でも、担当者や組織変更が起これば最初からコミュニケーションを設計する必要があるため、「自治体だから難しい」わけでなく「法人営業ならあり得ること」と捉えることができるでしょう。
予算スケジュールへの対応
自治体営業における予算スケジュールへの対応は、法人営業における期末商戦や大企業の年度計画対応に似ています。
自治体は年度ごとに予算が決定・消化されますが、大企業も同様に年度末や四半期末に調達判断が集中するケースがありますよね。
自治体営業で「この時期は動きが悪い」「ある時期に一気に話が進む」といった傾向は、民間の法人営業でも「期末商戦」や「決算前の駆け込み発注」といった形で起こります。
つまり、予算スケジュールへの対処は特別なことではなく、法人営業における季節性や予算を意識した戦略立案と同様です。
むしろ、全国の自治体が同じようなスケジュールで運営されているので、自治体営業の方が簡単だと言わざるを得ないでしょう。
透明性と説明責任
自治体営業における透明性と説明責任は、法人営業におけるコンプライアンス重視企業への提案と似た課題でしょう。
自治体は公的機関として公正性と透明性が求められ、提案を受け入れる際には説明責任が伴います。
これも、株主対応や社会的責任を強く問われる上場企業や新興規制業界における営業と類似しており、相手の求める透明性基準やプロセスを理解して対応するだけの話ですね。
最後に
「自治体営業は難しいか?」について書いてきました。
行政や公務員は必要以上に特殊化されているように感じていますが、自治体営業も同様です。
私個人的には「法人営業で活躍できる人は、自治体営業でもバッチリ活躍できる」と考えています。
官民のギャップに焦点があたる世の中ですが、少しでも自治体営業にチャレンジする方が増えたら嬉しいなと思います。
自治体営業で職員の方とやり取りする上で意識していることの記事などもありますので、併せてご覧いただけたら幸いです。