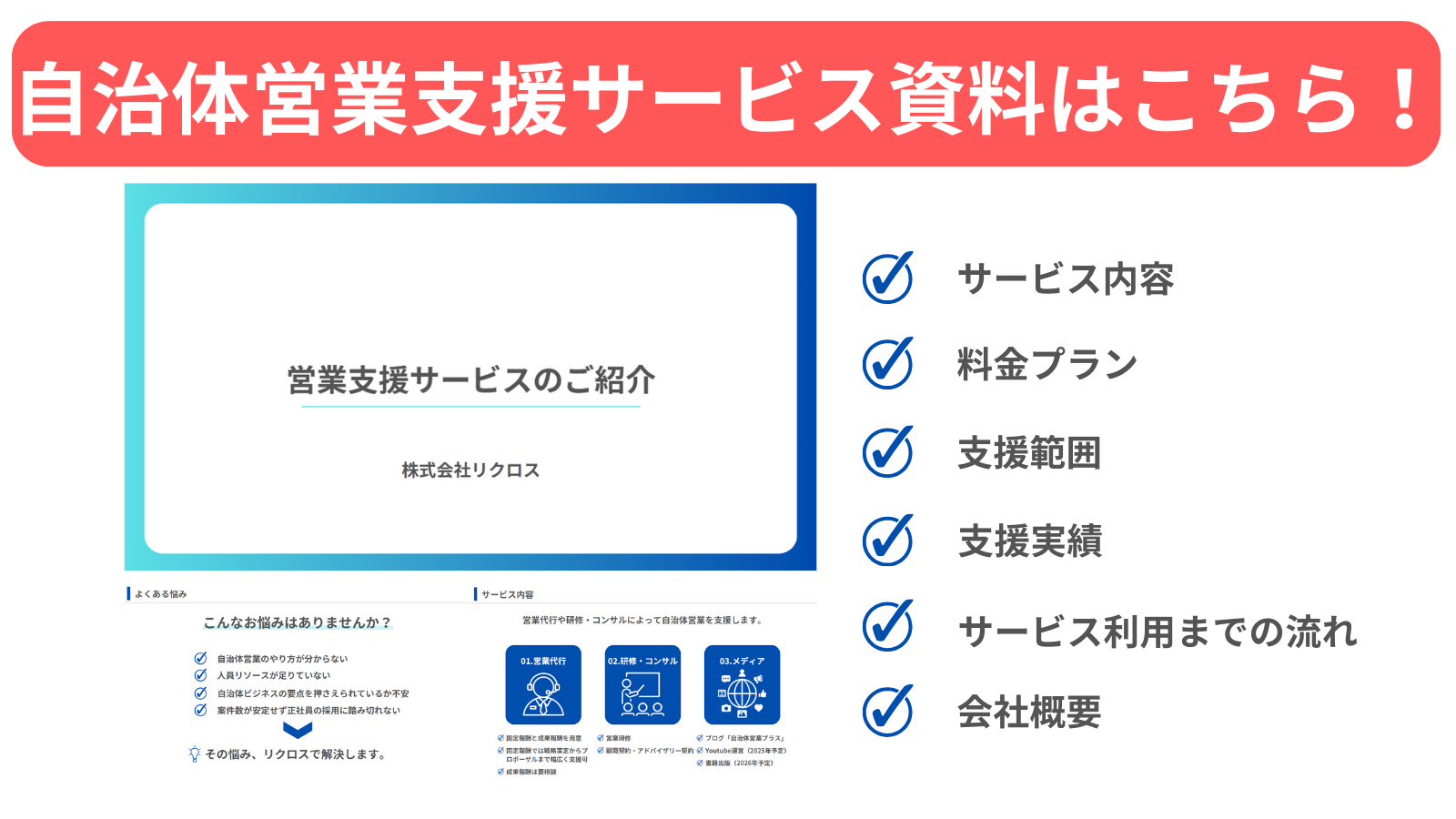はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、自治体営業のコツを7つのフェーズ×3つのポイントで解説していきます。
これまで自治体営業に関する記事をいろいろ書いてきましたが、本記事はある意味サイトマップのような内容となります。
私自身、市役所と出向先の中央省庁で営業を受け、転職後にリクルートで法人営業をやり、現在は企業様の自治体営業を支援しています。
それらの経験を活かして、企業の皆様の営業活動を振り返る際にチェックするような記事にできたらと思いますし、今後も適宜アップデートしていきます。
それでは見ていきましょう!
自治体営業の7つのフェーズ
自治体営業の7つのフェーズは以下のとおりです。
(1) 事前準備・情報収集
(2) アプローチ手法の確立
(3) 初回コンタクト(テレアポ)
(4) 打ち合わせ
(5) 予算要求フォロー
(6) 入札・プロポーザル対応
(7) 受注後対応
前提として、営業対象が広い(全国)ことや、事業者選定時にプロポーザルが実施されることを想定しています。
上記7つのフェーズを元に、自治体営業のコツとしてそれぞれ3つのポイントを挙げていきます。
事前準備・情報収集
余計な事前準備・情報収集をしない
まず重要なのが、余計な事前準備・情報収集をしないことです。
「日本人は詰め込み教育によりインプットに偏りがちで~」などと言うつもりはありませんが、ついついインプットしてしまう方がいるのは間違いないでしょう(私も昔そうでした)。
また、公平性や透明性の観点から、行政の情報は基本的に公開されているものが多いので、やろうと思えば大量のインプットができてしまいます。
予算書や施策方針、基本計画、ホームページ情報などは一定のインプットとして有用ですが、明確な目的なしに広く浅く情報を集めると、結局使わないデータで頭が埋まります。
必要最低限の情報から入り、後は実際にコンタクトを取ってから得られる生の情報で肉付けするほうが効率的です。
表に出ている情報だけで判断しない
自治体の総合計画に記載があるからといって必ず実施するとは限りませんし、記載がないからといって実施しないとも限りません。
また、ある課が使っているシステムが単年度契約だとしても、5~10年の活用を見越していることなんかもよくあります。
幸いなことに、明確な意図を持って自治体職員の方にヒアリングすれば教えてもらえることが多いので、公表情報だけで諦めずにアプローチを重ねてみると良いでしょう。
自社サービスに関連する情報は(さすがに)チェックしておく
これは言うまでもないですね。
その分野のプロではないかもしれませんが、少なくともそのサービスに関してはプロだと自信を持って言える程度の情報収集は最低限しておきましょう。
具体的には、関連する制度、類似サービスの導入事例、自社の強み弱み、市場動向やトレンドなどです。
自治体職員は行政のプロですが、特定の分野やサービスについては必ずしもプロではないというのが私の認識です。
是非自治体の意思決定をサポートしてあげましょう。
アプローチ手法の確立
テレアポでダメなら全部ダメだと割り切る
自治体への初回コンタクト方法はいろいろありますが、テレアポで上手くいかない場合、サービスまたはやり方の少なくとも片方が筋が悪いとご認識ください。
やけにはっきり書いていますが、様々な商材を営業支援した経験から自信を持って言えます。
法人営業におけるテレアポからのアポ率は0.5%~1%と言われていますが、自治体営業においては少なくともその10倍だと思ってください。要するにアポ率5~10%ですね。
自治体営業のテレアポのコツやトークスクリプト作成のポイントについては別途記事にまとめています。
また、自治体営業のリストも定期的に見直しましょう。
他の手法を試す価値がないわけではない
他の手法としては、オンライン商談、フォーム営業・メール営業、対面商談、飛び込み、トップアプローチ、媒体掲載などが挙げられます。
自治体営業におけるテレアポは野球でいうストレートだと考えています。
ストレート(テレアポ)とカーブ(オンライン商談)だけで試合は組み立てられますが、それ以外の球種も活用方法次第では有効ですので、是非自社に合ったアプローチ手法を模索してください。
各アプローチの概要については別途記事を用意しますね。
トップや議員へのアプローチは細心の注意を払う
行政は上意下達というイメージを多くの方がお持ちかと思います。
「だったらトップや議員へアプローチすれば一気に話が進むのでは」と考える方も多いでしょうが、細心の注意を払って進めましょう。
やらされ仕事を「責任を感じなくて楽」と考える人はいるでしょうが、「やらされて楽しい」と思う人は少数派かと思います。
自治体職員の意中の一社に決定させるためのアクションがあるということは、決定させないためのアクションもいくらでも取ることができるということ。
表に出てはまずいやり方で進めるのは控えた方が良いでしょう。
初回コンタクト(テレアポ)
アポ獲得をゴールとする
テレ「アポ」なので(言葉の定義からして)アポ獲得をゴールにするのは当たり前ですが、必ずゴールから外れないようにしましょう。
資料送付はゴールではありません。アポ打診した結果、資料送付になるのはOKです。
資料送付しただけで勝手に予算要求してもらえることはほとんどありませんので、商談時間を妥協してでもアポ打診しましょう。
例えば、商談を通常60分と設定しているところ、30分や15分に妥協してでもアポを提案し、短い時間で訴求しつつ、顔を見せて関係構築しましょう。
シンプルにそぎ落とす
地味ですが非常に重要なポイントです。弊社メンバーの状況をチェックする際にも最優先で見るポイントです。
シンプルであることで時間効率が良くなり、自治体職員にとっても時間が短く済みます(量)。また、しっかり内容を理解されアポなどに繋がりやすくなります。また、相手に刺さる一言を磨くことができます(質)。
どこまでそぎ落とすかと言うと、(第一声の)「お世話になっております。」や「株式会社」なども削る対象です。
とにかく短く、とにかくシンプルに。テレアポだけでなく営業活動全般に活きる心構えだと自信を持って言えます。
仮に自治体営業3原則を作るとしたら「シンプル、スピード、接点量」(3つのS)です。法人営業や個人営業も同じようなものかと思いますので、営業の鉄則と言えるでしょう。
切り返しは改善の余地が(かなり)あると考える
切り返しトークの巧拙だけでアポ率が1.2倍は変わります。低く見積もってです。
具体的なトーク内容は商材にもよりますが、商材によらない共通のポイントとしては、自治体職員に配慮はしつつ遠慮はしないという点です。
弊社は自治体営業の代行をすることが多いですが、単発のコンサルティングなども対応できますので、スクリプトや切り返しトークでお悩みの企業様はご遠慮なくお問い合わせください。
打ち合わせ
対面とオンラインはうまく使い分ける
対面での打ち合わせは信頼構築には効果的ですが、スケジュール調整が難しい場合や地理的制約がある場合はオンラインも活用しましょう。全国の自治体が営業先だと旅費交通費もかかりますよね。
弊社のご支援先で言いますと、最初から最後まで基本的にはオンライン、最初からずっと対面、最初はオンラインで興味を持たれた自治体は次回以降対面、注力地域は対面などいろいろあります。
時間やお金、体力などと相談して最適な形を模索しましょう。
まずは提案してみる
営業におけるヒアリングは基本のキですが、自治体営業ではまずは提案してみるつもりで挑みましょう。
自治体職員は人事異動が早いことや目先の業務で忙しいこともあり、そもそも意見を持っていなかったり考えたことがなかったりすることが珍しくありません。
まずは一度情報提供して、相手の反応を見て今後のアプローチ方法を検討しましょう。
提案資料はオーソドックスでOK
自治体営業の資料の記事にも書きましたが、提案資料はオーソドックスで構いません。
自治体営業だからと言って「総合計画が~」「公益性が~」「地域の課題が~」など、内容自分から複雑にする必要はありません。
上記内容よりも「市長や上司がそう言った」「議会で指摘された」「単純に導入すると良さそう」あたりの背景で導入することが多いのがリアルなところです。
ただし、国や県の動向、導入実績は意思決定に関わってくる内容なので盛り込みましょう(特に実績)。
予算要求フォロー
提案資料はそのまま使われないと想定する
自社が出した提案書が、そのまま内部説明に使われると思わない方がよいでしょう。
担当者が予算要求するにあたっては自前の資料が作られます。その際に活用しやすい情報をあらかじめまとめておくと、自治体職員も助かります。
提案資料(詳細版)として20ページや50ページの営業資料を用意される企業様が多いかと思いますが、全ては使われないので、概要版を用意するか、詳細版から抜粋されてもいいような構成にしましょう。
こちらも自治体営業の資料の記事にまとめました。
職員の発言を真に受けない
3月議会の承認を持って当初予算案が確定するので、それまでの職員の発言は真に受けないようにしましょう。
信頼関係があったとしても本当のことを伝えてくれないこともありますし、信頼関係がない企業に対して前向きに聞こえる発言をすることもあります。
接点が途切れないようにする
職員が言いたいことが言えない状況だとしても、企業側から伝えるべき情報をしっかり伝えることはもちろん可能です。
「自治体営業は9月までに済ませましょう!」といった発信もたまに見られますが、それだと3月議会で当初予算が確定するまでの半年間、営業活動がストップしてしまいます。
自治体営業は接点回数がカギなので、是非適切に関係構築しましょう。
入札・プロポーザル対応
事前のマイナス印象は引き継がれると思い気を付ける
自治体の事業者選定プロセスはフェアです。行政が公平性や透明性を重んじるのは言うまでもないですよね。
ただし、採用試験で言うマークシート方式(完全に機械的に優劣を決める)というよりかは、面接方式(機械的なチェックポイントもあるが、面接官の主観の寄せ集めで優劣を決める)の方が実態に近いです。
事前の態度が明らかに悪い就活生がいたら面接官にその情報が伝わるのは当たり前ですし、過去の経歴(事業者の実績)を見るのも当然でしょう。
自治体営業に限らずですが、最初から最後まで誠実に向き合いましょう。
意外と逆転できると知る
仕様書作成から関わっている事業者がプロポーザルにおいても有利なのはほとんどの企業様がご存知かと思います。
しかし、世間的に思われているよりかは十分逆転可能というのが私の認識です。
実際に知人に1時間程度アドバイスしただけで受注が決まった実績もありますので、是非諦めずに取り組んでみましょう。何かございましたらご遠慮なくご連絡ください。
提案内容はとにかく分かりやすくする
当たり前のように聞こえますが非常に重要です。
具体的にどの程度分かりやすくするかと言うと、「電車でたまたま隣に座っている方が企画提案書を読んでも、ネット検索せずに理解できるレベル」くらいが良いかと思います。
プロポーザルの選定委員と言っても、事業者様が提案するサービスについて深い知見を持っていないことがほとんどです。
これはプロポーザル選定委員の決め方を知れば理解できるので、是非記事をチェックしてみてください。
受注後対応
最低限、仕様書の通りに活動する
言うまでもないですが、あえて書いておきます。
民間同士のやり取りであればもしかすると「仕様通りじゃなくても、納品物が結果的に良くなるのであればいいよ」といった融通が利くかもしれませんが、行政は違います。
プラスアルファのサービスをすると喜ばれるかもしれませんが、まずは仕様を満たすことを怠らないようにしましょう。監査の指摘を受けますし、大きなトラブルの元になる恐れがあります。
とにかく安心感を与える
仕様を完全に満たすことで合格点(「可」)を取り、とにかく安心感を与えることで「優」「良」を狙うイメージです。
契約を果たせば行政としては問題ないですが、自治体職員も人間です(当然ですが)。
問合せへの迅速な回答、定期的な進捗報告など、「この会社なら任せても大丈夫」と思わせる細やかな配慮が次の実績に繋がりますので、受注後もやるべきことをしっかりやりましょう。
良い噂も悪い噂も他(部署、自治体)に伝わると思い気を付ける
公務員インタビューにもありましたが、ある事業者の噂は役所内部でも役所間でも共有されます。
実績が実績を呼ぶのが自治体ビジネスの魅力の一つですが、逆に言うとマイナスがマイナスを招くことも。
最初から最後まで気を抜かずに活動していただければと思います。
最後に
自治体営業のコツを7つのフェーズ×3つのポイントでまとめました。
今回のまとめ記事が自治体ビジネスに取り組む企業様のお役に立てば幸いです。