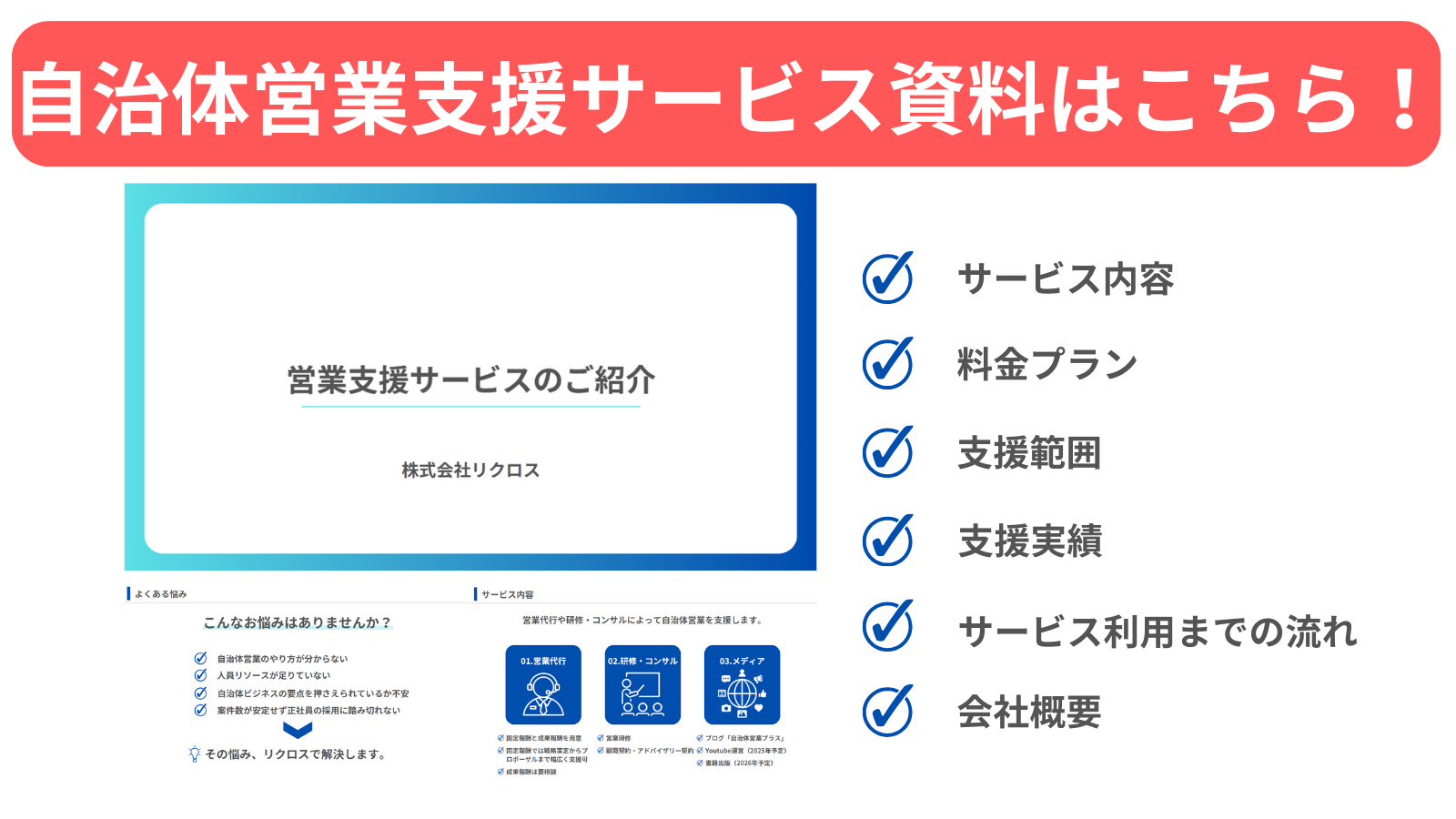はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は自治体営業のスケジュールについて書いていきます。
私自身、これまで市役所と出向先の中央省庁で営業を受け、転職後はリクルートで法人営業をやりました。その経験を活かして自治体営業の支援会社を立ち上げ活動しているわけですが、経歴的には自治体営業を語る適任者だと自負しています。
本メディアは自治体営業をテーマとしているのでネットなどで情報収集する機会が当然多いわけですが、自治体営業に取り組まれる企業様にいちばん誤解してほしくないのは、まさに自治体営業のスケジュールの部分です。
「自治体営業 スケジュール」というキーワードで情報を探すと、多くの場合は「予算編成時期を狙って営業をかけるべき」という内容が目につきます。
もちろん、自治体は予算という大きな枠組みの中で事業を進めるため、限られた時期に的を絞ってアプローチすることは重要です。
しかし、実際の現場では“年度のどのタイミングでも相談を受け付け、案件の進め方を検討している”ということも少なくありません。
そのため、予算編成時期を中心とした“王道パターン”だけでなく、“通年パターン”でコンスタントに関係性を築いていく営業手法も非常に有効だと考えています。
本記事では、自治体営業におけるスケジュールの重要性を整理したうえで、予算編成を軸にした王道パターンと年中アプローチする通年パターンを比較し、さらにリソースが限られている場合の対策・工夫についても掘り下げていきたいと思います。
それでは見ていきましょう!
自治体営業におけるスケジュールの重要性
自治体の特性と意思決定プロセス
自治体は、国や都道府県の方針・財政状況、地域住民の声などを反映しながら事業を進めます。特に、予算化のプロセスと議会の承認を経なければ新規事業や施策を導入できない場合が多いというのが特徴です。
このように、財政と議会審議を経て初めて公的資金を使うことが可能になるため、営業活動もそのプロセスに合わせたアプローチが効果的だとされています。
スケジュールを把握することのメリット
営業活動の効率化の一言に尽きます。
予算編成から議会審議のタイミングを理解しておくことで、「いつ」「誰に」「何を」提案すれば受け入れられやすいかを把握しやすくなります。不要な時期に無理に営業をかけるよりも、的確にタイミングを測ることで効率が上がります。
また、担当者が何に忙殺されている時期か、あるいはどの時期が比較的話を聞いてもらいやすいかを知っていれば、同じ提案でも話の進み方が変わってきます。業務の繁閑を意識することは、担当者との信頼関係を構築するうえでも欠かせないでしょう。
さらに言うと、全国の自治体が同じようなスケジュールで動いていることも大きいですね。1つ知れば(ほぼ)全部を知れるのは自治体営業ならではだと思います。
自治体の予算編成スケジュール
自治体の予算編成プロセスは、大まかには以下のような流れで進みます。細部は自治体によって異なる場合がありますが、多くの自治体で似たような年間サイクルが存在します。
なお、ネット上に出回っている情報よりかは、自治体によって予算要求などの締切月が異なりますので、季節による表記とさせていただきます。
情報収集・予算要求(春~秋頃)
自治体内部で各部署が翌年度の事業や施策に必要な予算を洗い出し、財務担当や首長(市町村長・知事など)へ要望をまとめていきます。
この段階で事業の必要性や具体的な内容をある程度固めていくケースが多いですが、「ある程度」という点に注意しましょう。内容があまり固まっていない状況で予算要求して予算額が確定してから本格的に内容を固めていくことが、一般的に思われているよりかは多いです。
予算査定(秋~冬頃)
財政部門や首長・副首長が優先度を考慮して調整を行います。限られた予算のなかでどれを重視するか、どれくらい削るかを詰めるため、ここで事業の継続や新規導入の可否がほぼ固まります。
議会審議(冬~年度末)
次年度の予算案が議会に提出され、審議されます。議会で否決されない限り、多くはここで最終確定し、翌年度の施策実施が決定します。
自治体営業スケジュール①王道パターン
上記の予算編成の流れをベースにすると、多くのサイトで言われている“王道パターン”は、予算編成スケジュールの「情報収集・予算要求(春~秋頃)」に「情報提供・予算要求フォロー」する自治体営業のスタイルとなります。
一方で、それ以降の「予算査定(秋~冬頃)」「議会審議(冬~年度末)」の時期に一切営業しない企業様がいたら個人的に大きな課題だと考えています。
「予算要求の時期だから営業しました」は全く間違っていませんが、本当にその時期だけのアプローチで良いのでしょうか。
別の例で言うと、部活の大会や受験の直前数か月が大切なことは一切否定しません。しかし、大会や受験で本当に成果を出そうと考えたら、1年間通して継続的に取り組んだ方が有利なのは言うまでもないでしょう。
王道パターンのメリット
限られたリソースでも成果を狙える
特に中小企業の場合、営業人員や時間が限られていることが少なくありません。予算編成の山場だけ集中して営業を行うことで、ピンポイントで案件を狙いやすくなります。
自治体担当者の動きと合致しやすい
予算要求の時期にアプローチされると「ちょうど新年度の施策で必要な情報だ」と受け止められ、話が通りやすいでしょう。
王道パターンのデメリット
他社も同じ考えで動く
この時期は他社も同様に動くため、競合が激化し、自治体担当者にとって営業アプローチが増えすぎる可能性があります。
想定外の案件を取りこぼす
予算編成外のタイミングや小規模予算、補正予算などで十分に検討してもらえる機会を逃してしまうことがあります。
自治体営業スケジュール②通年パターン
“通年パターン”は言葉の通りなのでイメージしやすいでしょう。
予算編成や議会の時期にかかわらず、常に自治体担当者との関係を継続的に育んでいく営業スタイルを指します。
具体的には、定期的な情報交換や軽いミーティング、メールでの近況報告、ニーズ確認などを行い、常時「自治体の課題解決に寄り添う体制」を整えておく考え方です。
接点回数を確保して信頼関係構築していくやり方ですね。
通年パターンは、短期的には費用対効果が見えにくい側面もありますが、自治体営業を長期的に考える場合には非常に有効な戦略となります。
通年パターンのメリット
信頼関係構築
通年でやりとりしていると、担当者からすれば「困ったら相談できる相手」として認識しやすくなります。
予算の増減やイレギュラーな案件への対応
自治体には補正予算や国の助成金による緊急対策など、イレギュラーな予算追加が行われることがあります。こうしたタイミングでいち早く声がかかるよう、常日頃から連絡を取っていれば、思わぬ受注につながるケースもあります。
競合との差別化
予算要求時期だけ営業活動する企業が多い中、通年でフォローアップする姿勢は差別化ポイントです。「困ったときにまず相談したい」と思ってもらいやすく、競合との比較で優位に立てます。
通年パターンのデメリット
リソースの管理
通年でアプローチするには、電話やメール、訪問などの回数が増えるため、それなりの営業リソースが必要となります。
より高度な営業力が必要
通年でアプローチするという姿勢が“無理な売り込み”だと捉えられないよう、常に相手の状況を理解し、寄り添う姿勢を持つことが重要です。
リソースが限られている場合の対策・工夫
営業リソースが潤沢でない場合はどうすればよいのでしょうか。ここでは、そのような状況でも「王道パターン」と「通年パターン」を上手にハイブリッドで活用するための工夫を紹介します。
ターゲットの絞り込み
アプローチする自治体を精査することが大切なのは言うまでもないでしょう。
自治体ごとに力を入れている施策や人口規模、予算規模は違います。自社が持つサービス・製品の強みが最も活きる分野や事業に取り組んでいる自治体を優先的にリストアップし、重点的にアプローチを行いましょう。
自治体営業のアプローチ優先順に関する記事も合わせてご覧ください。
王道×通年のハイブリッド戦略
限られたリソースのなかで、どうしても年間を通じて全自治体にアプローチするのは難しいという場合には、「主要ターゲットには通年パターン、その他ターゲットには王道パターン」など使い分けましょう。
外部リソースの活用
弊社のような営業支援会社やコンサルタント、あるいは既に自治体と実績があるパートナー企業に部分的に外注や協力依頼するのも手です。
最後に
自治体営業のスケジュールについて書いてきました。
私が今回の記事で実現したいことは、王道パターンに偏っている自治体営業を通年パターンに寄せていく企業様が増えることです。
サイト紹介に書いた通り、自治体を変えられるのは民間企業だと強く信じています。
少しでも自治体営業のレベルアップに繋がり、結果として自治体やその地域の住民の方々のためになることを願い、本記事を終わりとさせていただきます。