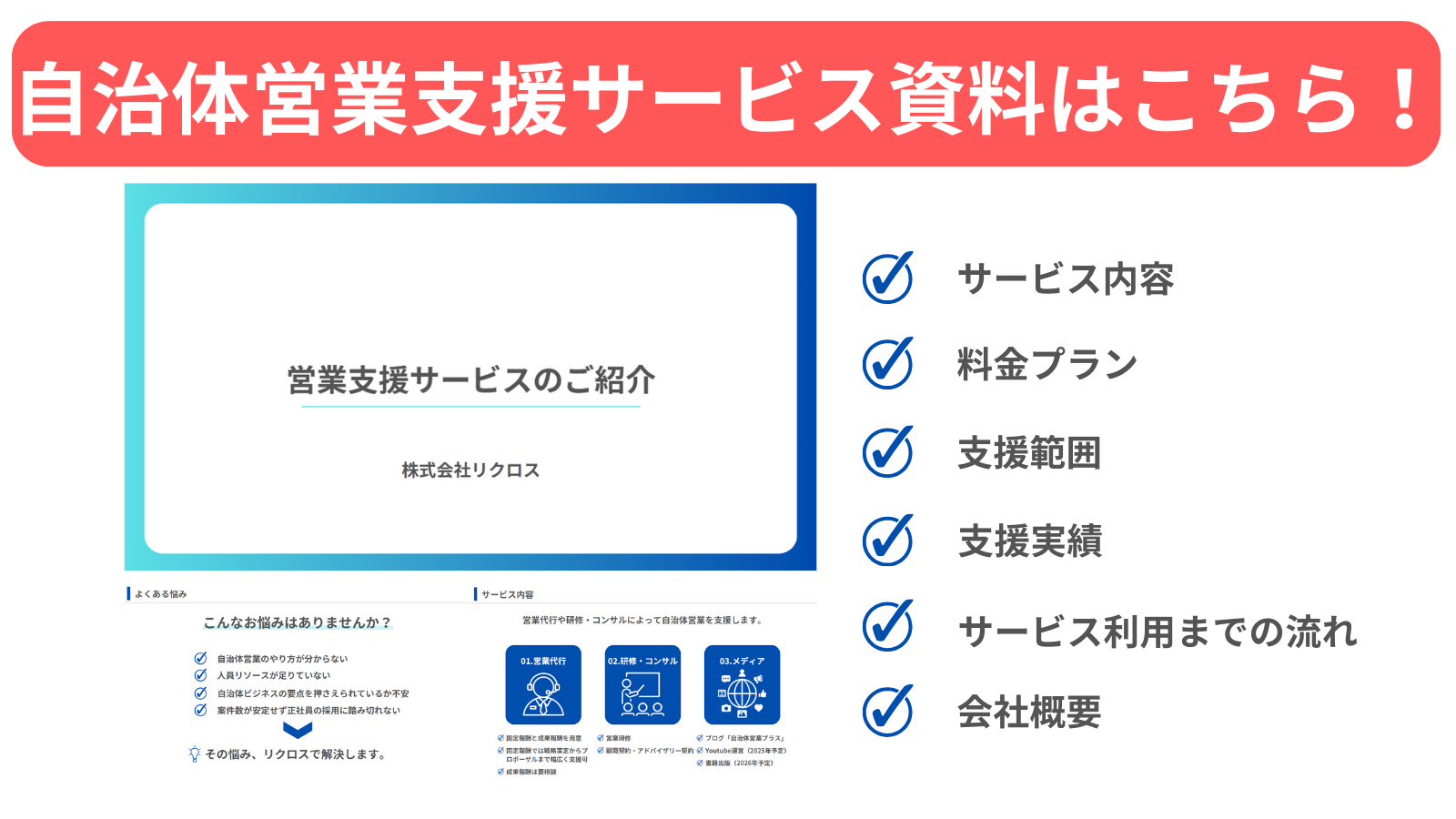はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は企業インタビュー第三弾として、株式会社Empathy4uの森岡社長にお時間をいただきました。
Empathy4u様は約半年前の2024年6月に会社を設立されたばかりで、弊社が10月からご支援させていただいている企業様です。
参入を決断されたきっかけなど、自治体ビジネス参入を検討されている企業様の参考になるかと思いますので、是非最後までご覧ください。
自治体ビジネスの魅力の記事もございます。
それでは見ていきましょう!
インタビュー
会社設立の背景
木藤:森岡さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。早速ですが、会社設立の背景と現在の事業内容について教えていただけますか?
弊社は、元々私が前職で行っていたSNS相談事業を基盤として設立しました。SNS相談は、LINEなどを活用して子育てや教育、さらにはヤングケアラー支援など、幅広い分野の相談を自治体向けに提供する事業です。この事業を通じて、特にヤングケアラー支援がうまくいっていない現状を痛感していました。
ヤングケアラー支援においては、政府が予算を組み自治体の後押しをしている一方で、自治体では広報や実態調査が進まず、支援が形になっていないケースが多い状況でした。この課題を解決するために、自治体に実態調査のシステムや居場所づくり、SNS窓口などを提供するビジネスをスタートしました。
木藤:ありがとうございます。Empathy4u様の紹介についてはnoteにも詳しく載っていますので、興味があれば是非お読みください。さて、自治体ビジネス参入はなかなか大きな決断だと思いますが、「参入しよう」と決断できたポイントを教えていただけますでしょうか?
大きなポイントは2つあります。
まず1つ目は、元々SNS相談事業が幅広いジャンルで活用されており、既に市場が形成されていたことです。
ヤングケアラー支援という新しいテーマにおいても、こども家庭庁が大規模な予算を投入しており、明確な市場が存在していることが後押しとなりましたね。
例えば、今年度こども家庭庁がヤングケアラー支援に177億円もの予算をつけていることから、自治体としても取り組みを進めていく流れがあると感じました。
2つ目として、自治体向けの実態調査の仕様書や単価が事前に把握できていたことも、参入を決断できた理由の一つです。
案件の規模感や予算の動向が具体的に見える中で、「これならビジネスとして成立するのでは」という考えを持てました。
特に今年6月にヤングケアラー支援法が改正され、自治体が対応を迫られるタイミングと自社の設立タイミングが合致したことも大きかったですね。
木藤:国や県の大きな動き(予算)があって、自治体が実際に発注しているとなると論理的な確信を得られますよね。これらの情報は公開されていることがほとんどなので、参入して自治体に良い影響を与える企業様が増えると私としても嬉しいです。
参入してこれまでどうだったかを伺いたいですが、元々前職が自治体ビジネスに取り組んでいたんですよね。
おっしゃる通り、前職でも自治体ビジネスには携わっていました。ただ、厳密に言うと営業よりもエンジニアとしての役割が中心でしたね。
最初の2〜3年は完全にシステム開発に専念しており、自治体と直接やり取りする機会はほとんどありませんでした。後半の2〜3年で徐々に自治体とのやり取りや、プロジェクト進行に関わることが増えたものの、営業活動としては限られた経験でした。
テレアポなどもほぼしたことがなく、問い合わせがきたものを対応するといった形でしたね。
自治体営業のセオリーは肌感としては分かっていた程度です。
自治体営業の取り組み
木藤:会社設立されて、実際にこれまでどのように自治体営業されてきましたか?
主にテレアポを活用し、自分でリストを作成して電話をかけていましたね。他の手法(展示会やFAXなど)は費用対効果を考慮して実施していません。一応前職の紹介を受けて共同提案などはあります。
木藤:私はよくお客様に「アポ取りはテレアポだけでも十分。それでアポが取れなかったらサービスかやり方が悪い」と言っています。実際にテレアポしていかがでしたか?
効果はあるけど楽ではないと感じましたね。
実際に自分でテレアポをしてみると、アポ率は20〜30%程度でした。数は多くないですが感触は悪くなく、自治体の担当者と直接繋がることができたことで、実際の案件に繋がる可能性を感じました。
一方で、心理的な負担が非常に大きかったです。私は元々エンジニアなので、知らない人に電話をかける行為自体が大きなストレスなんですよね。実際に電話をかける前には深いため息をついたり、気持ちを切り替えるのに時間がかかることもしばしばありました。
また、テレアポにはまとまった時間が必要です。しかし、エンジニアとして開発業務を抱えている中で、合間にテレアポを挟むと作業の効率が落ちてしまうことが課題でした。
木藤:全て同じ意見です。テレアポは営業支援会社の代表の私ですら億劫なんですよね(笑)業務の合間に気軽にできるものではないというのもすごく分かります。その後弊社にアウトソースいただいたわけですよね。
そうですね。テレアポ業務をアウトソースしたことで、心理的負担や時間的な制約が軽減されました。
また、自分が直接やるよりもアポ率が向上(20~30%→35.4%)したので営業効率が向上しましたね。委託先が自分よりも上手く営業できると思っていなかったです。
木藤:お力になれて嬉しいです。一般的には「あなたの会社以上に営業代行会社が売れることはない」という意見もあるようですが、弊社は今のところは全くそんなことないですね。森岡さんのアポ率(20~30%)がはっきりしないですが、仮に23.6%なら1.5倍の成果(35.4%)が出たことになります。
アポを取った後は対面で商談されていますよね。やってみていかがでしょうか。
自治体によって本当にバラバラだと感じます。
「国がこう言っているからAだ」という自治体もいれば、「国はこう言っているけどうちはB」という自治体もいたり。
同じ県内の自治体であっても温度感が全然異なっていたり、国の通達の解釈が異なっていたり。
近隣自治体を見ている自治体もいれば、他の自治体の動きが分からず困惑している自治体もいる。
商談に行けば名刺すらもらえないこともあり、逆に部長まで参加されることもあり。
木藤:アプローチしてみないと分からないことだらけですよね。自治体のHPに情報がいろいろ載っていても、担当者の熱量が低いというだけで話が進まないこととか全然あります。
ちなみにアプローチしていたのは人口10万人以上の自治体なので、比較的先進的な取り組みをやっていてもおかしくない自治体ですね。
すでに40自治体以上とお話できたので、「ヤングケアラーについて私より詳しい担当者の方はなかなかいないだろうな」という感覚があります。
木藤:自治体は「内部でやると決めたから情報収集する」という傾向がありますが、個人的にはもっと気軽に、森岡さんのような方から「話を聞いてから検討する」という動きが増えるといいなと思っています。自治体職員は行政のプロであって分野やサービスのプロではないという認識なので、分野やサービスについてはどんどん民間企業の話を聞いてほしいですね。
11月に商談したらすぐに補正予算に入れ込んでくれようとした自治体もありましたね。
木藤:自治体営業のスケジュールの記事にも書きましたが、そういったチャンスを掴むためにも是非通年で自治体と接点を持ってほしいですね。
今後の展望
木藤:最後に今後の展望をお聞かせください。
まだ会社設立半年しか経っていないので、まずは実績を積み重ねることを重視し、地道にアポイントを取って接点を増やしていく方針です。いろいろ情報も集まってきているので、将来的にはこども家庭庁と話ができたらと思います。
木藤:どうしても地道にアポ取っていくしかないですよね。残念ながらウルトラCはないです。役所のPCはセキュリティーの関係でWebマーケとかできないようなものなので。剣と盾で戦うしかないです。
飛び道具は本当にないですよね。そもそもアプローチのバリエーションがないので竹やりで戦うしかないみたいな。
木藤:私は「剣と盾」と言いましたが、「竹やり」もいいですね(笑)キラキラしたことをやりたくなりますが、シンプルに電話でアポ取って、対面かオンラインで商談すればいいと思います。
今日はいろいろお話を聞けて良かったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に
株式会社Empathy4uの森岡社長にインタビューしました。
・国や県の動向を追いつつ、すでに予算がある部分に参入する
・営業はシンプルにテレアポでアプローチ
など、私自身の考えともすごく近く、自治体ビジネスの解像度がまた高まった気がします。
自治体営業のコラムを一気に書き上げていましたが、また別の企業様にもどんどんインタビューしたいなと思いました。
森岡さん、ありがとうございました!