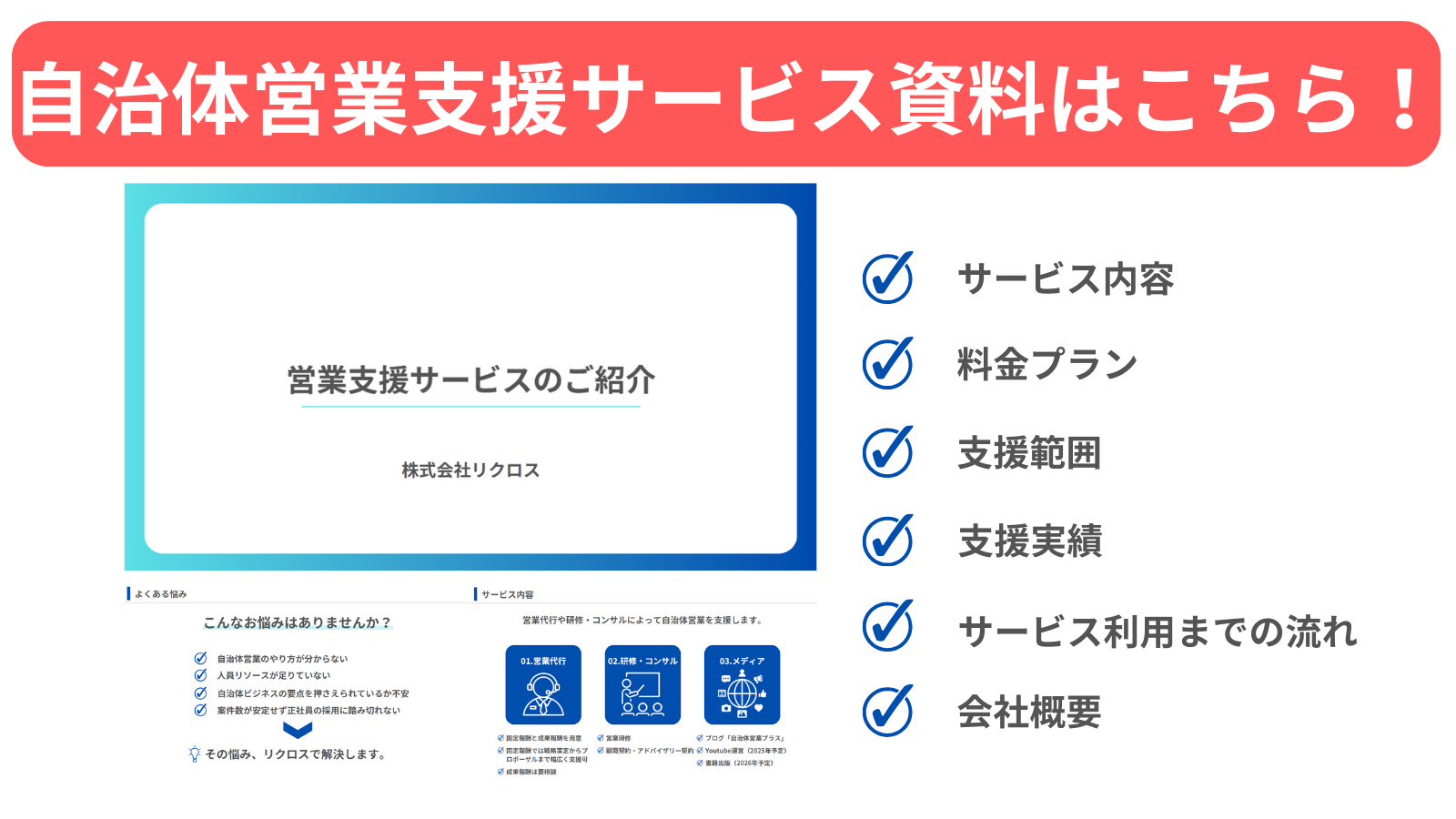はじめに
 木藤昭久
木藤昭久こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は公務員インタビューvol.6として、Kさんにお時間をいただきました。
元々は民間企業で営業を経験し、現在は市役所でお勤めのKさん。
私と同じく市役所&営業経験者として、意見が合う場面が多かったので、少しでも皆様の参考になれば幸いです。
それでは見ていきましょう!
インタビュー
これまでの経歴
木藤:Kさん、本日はお時間をいただきありがとうございます!早速ですがこれまでの経歴をお聞かせいただけますでしょうか?
大学卒業後、toC領域での営業職にて営業からマネジメントまでを経験しました。
その後転職して、市役所にて福祉関係の窓口部署に2年、現在は事業系部署にて補助金担当をしています。
木藤:ありがとうございます。民間経験があるのは存じ上げていましたが、まさかの営業職だったのですね。ちなみに市役所に入ってからは営業を受けた経験はあるのでしょうか?
もちろんあります。実際に電話であったり、窓口で営業を受けたことがあります。
木藤:差し支えない範囲でどういったサービスの営業を受けていたか教えてください。
コロナ禍だったこともあり、抗菌関係の営業やDX推進に関するシステムの営業が多かったと思います。
自治体営業のアドバイス
木藤:理解が深まりました。Kさん自身も営業経験があるということで、本メディアのテーマである自治体営業についてもご意見をお持ちかと思います。Kさんなりに「こうした方がいいよ」といったアドバイスがあればいただけますでしょうか。
私もそうだったのですが、入庁1年目は決裁ルートなどもわからず、異動1年目に営業を受けた際には、現所属の課題が何かを全体把握できていないため、聞くだけになってしまいました。
そのため、担当者が異動1年目かもしれないということを考えると、可能であれば上司(係長など)を同席させることや、担当者が異動して現所属の業務課題を把握した夏以降が話がスムーズかと思います。
また、自治体あるあるで、他自治体の導入事例を気にする傾向にあるので、他自治体の導入事例があるのが大事です。特に近隣市町村の導入事例があると有効ですね。
まずは先進自治体で実績を作り、近隣市町村へアプローチしていくことがいいのではと思います。
自治体へアプローチする期間について
木藤:ありがとうございます。アプローチタイミングの話が出てきましたね。変な質問をしてしまいますが、企業が自治体へ営業活動する際に、3か月や6か月だけアプローチすべき期間があるとしたらいつになるとお考えでしょうか。
年に1回だけアプローチするとしたらKさんがおっしゃる通り夏以降になるんでしょうけれども、企業の営業活動が年1回のみというのは営業の世界じゃあまりにも不自然なんですよね。競合との差別化も図らないといけないので、「年に何回でも接点(打ち合わせに限らない)を持つべき」というのが私の考えでして。
まず、3か月だけなら8月~10月ですね。理由としては、前述の担当者が慣れてきた頃から、当初予算の大枠がある程度決まる10月頃までが最短での営業かと思います。
次に、6か月だけなら5月〜10月ですね。まず異動して少し落ち着いた5月頃に営業を受けることで、サービス内容や営業に来られた方の話を聞く余裕があるかと思います。その上で、業務をする中で出てくる課題とサービスが結びつけば、導入を考えるかと思います。そのため、定期的に課題ヒアリングやサービスラインナップの情報提供があり、擦り合わせができれば10月頃に予算要求に繋がるケースがあると考えます。
他自治体の導入事例について
木藤:次に、他自治体の導入事例についてです。自治体経験者の方で、他地域での実績の重要性を否定する方はいないと思いますが、Kさんなりになぜ導入実績が必要なのかを教えていただけますでしょうか。
これは文化的なこともあるかと思いますが、新しいことを始める際には他自治体で実績があるのか問われます。でもこれは、税金を財源にするからこそで、他自治体での実績があることで、外部へも説明がつきやすいということかと思います。
財政的にも厳しい自治体も多いため、財政としてはいかに予算をカットしていくかを考えているため、財政課を納得させるためにも他自治体の導入事例がほしいという担当部署の思惑があるかと思います。
木藤:説明しやすさは本当に重要ですよね。「外部」というのは当然住民も含まれていると思いますが、やはり「あそこの自治体でもやっている!」というのは説明能力が高いです。冷静に考えると、他の自治体がやっているからといって良い取り組みとか良いサービスとは限らないわけですが、異様な話の通りやすさがあるといいますか。
だからこそ、Kさんのおっしゃる通り「まずは先進自治体で実績を作り、近隣市町村へアプローチしていくのがいい」んですよね。
さらに補足すると、人口規模が小さい自治体だけで広まっているというサービスはあまりないように思います。市町村は国や都道府県の動向を見て仕事しますが、同じ市町村同士であっても、より人口規模の大きな市町村の動きを見て物事を決める印象です。この点について、Kさんのお考えはいかがでしょうか?
私も同じ感覚です。
現職は比較的小規模自治体のため、県庁所在地など県内でも大きな自治体で導入実績があるかを確認します。そのため、人口規模の大きい自治体が導入して、1,2年遅れでサービス導入したケースが多いように感じます。人口規模の多い自治体で成功事例があると、市町村同士は横のつながりもあるため、営業を待たずに問い合わせるケースもありますね。また規模と合わせて、隣接する市町村の状況を確認するケースが多いです。
木藤:「営業を待たずに問い合わせる」は、企業にとっては理想の形ですね。自治体ビジネスにおいてインバウンド営業のみで成り立つ企業の特徴について記事を書いたことがありますが、まさに自治体間の紹介の連鎖が生まれるんですよね。今日はいろいろお話を伺えてよかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。